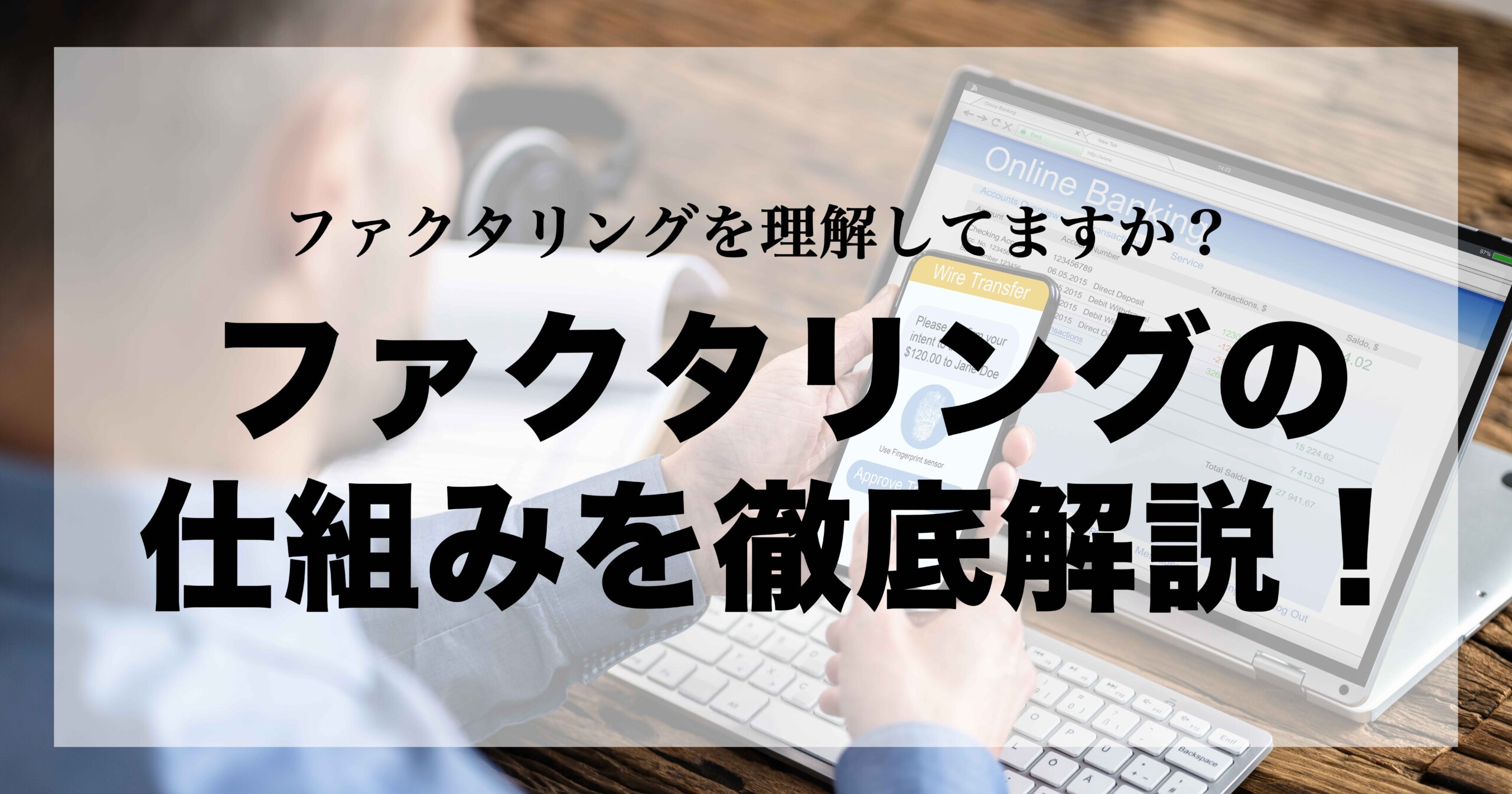資金繰りに悩む企業が利用する資金調達手段として、「ファクタリング」と「手形割引」はよく似たイメージを持たれがちです。
どちらも“将来の入金を前倒しして現金化する”という点では共通していますが、対象となる債権や仕組み、リスクには明確な違いがあります。
この記事では、ファクタリングと手形割引の違いを初心者にもわかりやすく解説します。
なぜこの質問が多いのか
ファクタリングの普及が進む中、従来からある手形割引との違いがわからず、「どちらが有利?」「どっちを選ぶべきか?」といった疑問を抱く経営者は少なくありません。特に「請求書を現金化できるのは同じでは?」という混乱が生じやすいため、制度や仕組みの正確な理解が求められています。
ファクタリングと手形割引の違い【結論】
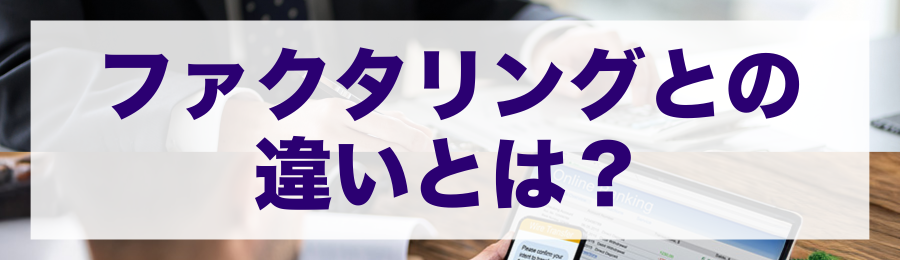
ファクタリングは「請求書(売掛債権)」を売却して現金を得る方法、 手形割引は「約束手形」を金融機関に持ち込んで、期日前に現金化する方法です。中でも即日ファクタリングは資金調達までの速さが異なります。
最も大きな違いは、「償還義務(返済義務)があるかどうか」です。
ファクタリングは売却扱いのため、原則として返済義務がありません。
一方、手形割引は金融機関からの“借入”に近く、手形が不渡りになった場合、利用者が支払う義務を負います(償還請求権あり)。
ファクタリングの仕組み
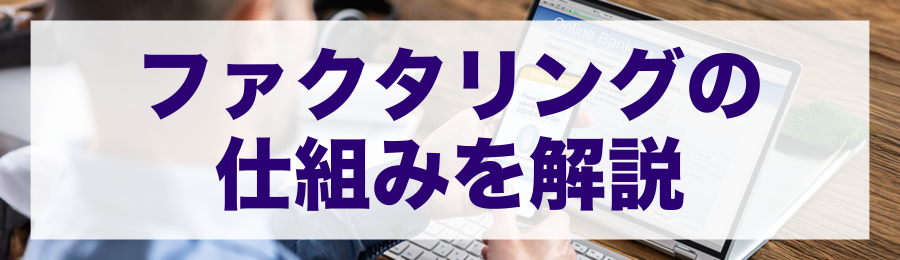
ファクタリングは、企業が持つ売掛債権(請求書)をファクタリング会社に売却し、支払期日を待たずに現金化する仕組みです。
売掛先の信用力が重視され、赤字や債務超過の企業でも利用できるケースがあります。
【特徴】
- 対象:請求書(売掛金)
- 契約形態:売買契約
- 償還義務:なし(ノンリコース契約が基本)
- 審査基準:売掛先の信用力
- 手数料:5〜20%程度(売掛先や契約内容により異なる)
手形割引の仕組み
手形割引は、将来一定期日に支払われる「約束手形」を、銀行や金融機関に持ち込み、期日前に額面から利息(割引料)を差し引いた金額を受け取る仕組みです。
【特徴】
- 対象:約束手形
- 契約形態:割引取引(実質は短期融資)
- 償還義務:あり(手形が不渡りになれば利用者が支払い)
- 審査基準:利用者自身と手形振出人の信用力
- 割引料:年利ベースで1〜5%前後(金融機関により異なる)
よくある誤解と注意点

「どちらも請求書を現金化するもの」と思われがちですが、手形割引は請求書ではなく「手形」という有価証券が対象です。
また、手形割引は「割引料」という名目ながら、実質的には借入と同様の性質を持ち、信用情報に影響を与える場合もあります。
一方で、ファクタリングは原則としてオフバランス(貸借対照表に負債計上しない)処理が可能なため、資金調達手段としての柔軟性が高いです。
リスク面の比較
- リスク:売掛先が倒産した場合、資金回収不能の恐れ(ただしノンリコースなら利用者の責任なし)
- 利用者側の信用力よりも、売掛先の信用が重視される
- 2社間ファクタリングは売掛先に知られずに利用可能だが、手数料は高め
- リスク:振出人が不渡りを出すと、利用者が支払義務を負う(リコースあり)
- 割引を受けた事実が信用情報に記録される可能性あり
- 銀行との取引実績があれば金利条件が優遇されることもある
実務での使い分けのポイント
- 短期的な資金繰り改善で、請求書がある場合**:即日ファクタリングが有効
- 取引先から受け取った手形を現金化したい場合**:手形割引を検討
- 償還義務や信用情報への影響を避けたい場合**:ファクタリングの方が適している
- 金利負担を抑えて現金化したい場合**:条件次第では手形割引の方がコストが低い
専門家によるアドバイスが有効な理由
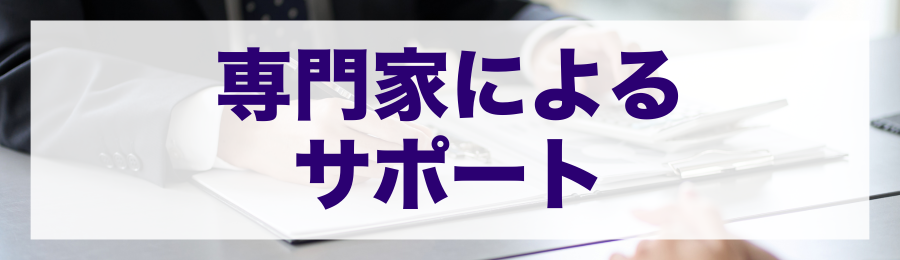
税理士や中小企業診断士は、資金繰り全体を見渡したうえで、ファクタリングと手形割引のどちらを使うべきか、または別の資金調達手段を組み合わせるべきかを判断するサポートが可能です。
まとめ:目的と信用状況に応じて正しく使い分けを
ファクタリングと手形割引は似て非なる資金調達手段です。 どちらにもメリット・デメリットがあり、自社の信用状況、資金ニーズ、取引先の状況などを総合的に考慮して使い分けることが大切です。
リスクと費用、信用への影響をよく理解したうえで、必要に応じて専門家に相談し、最適な資金戦略を立てましょう。